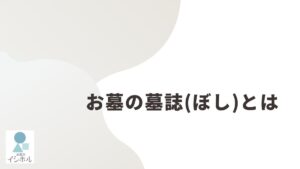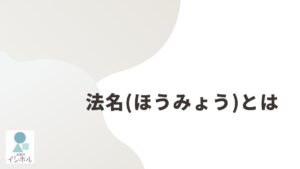戒名とは?意味や由来、授かる際の注意点を解説
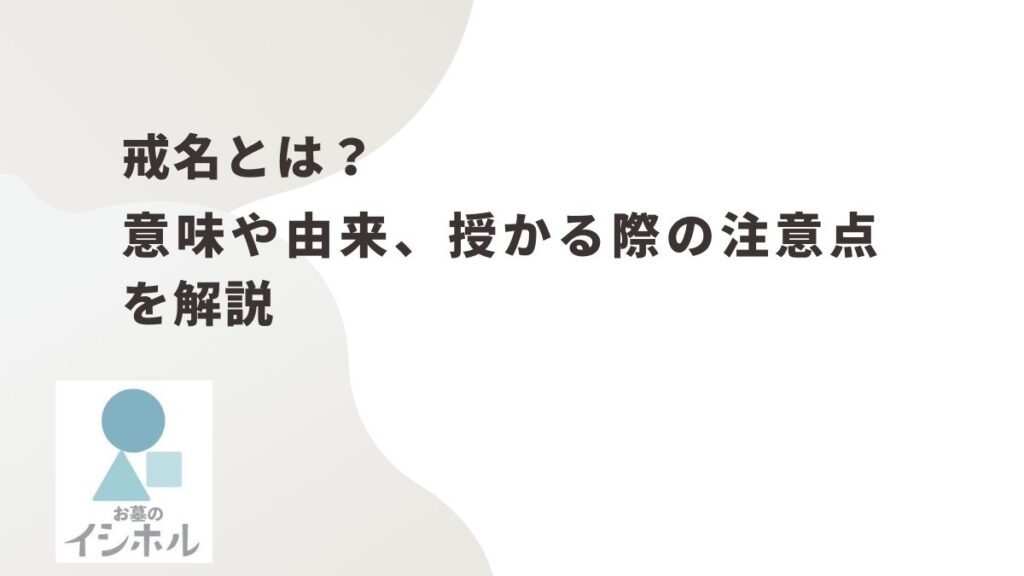
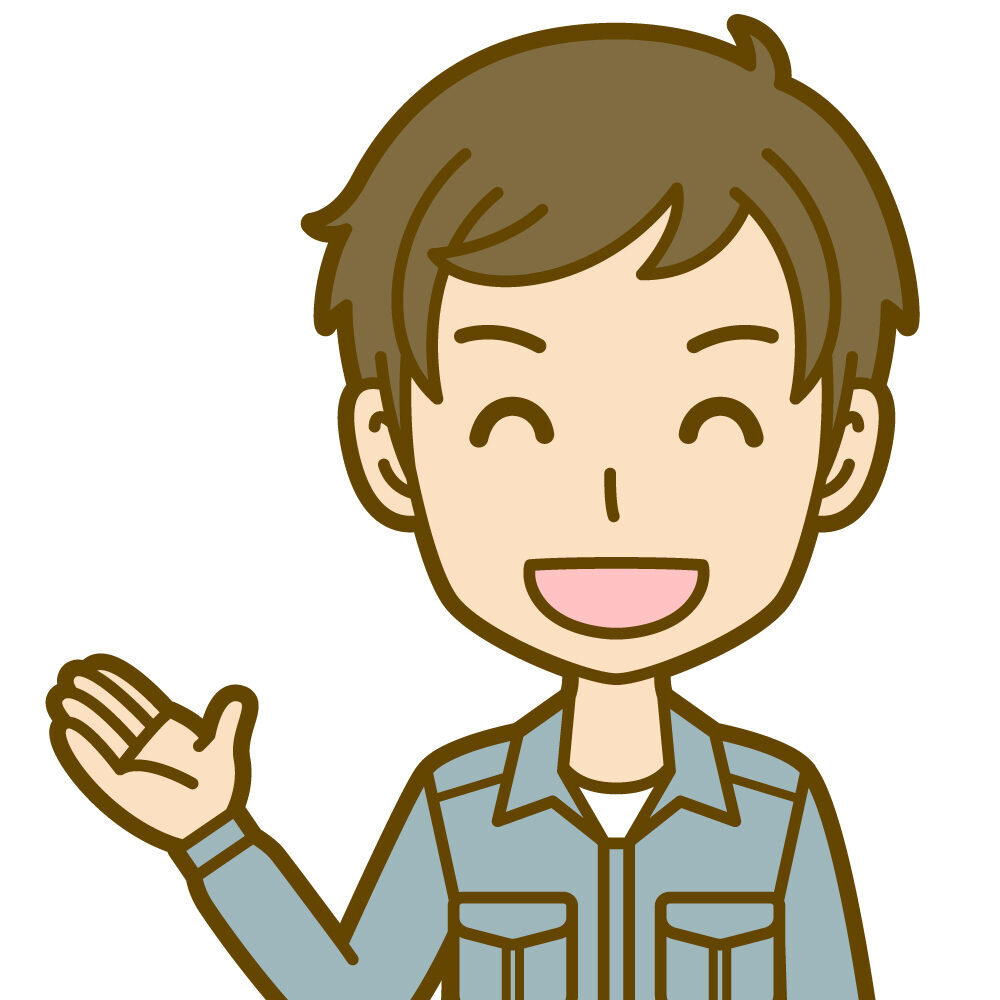
業界経験この道30年の石職人です。今回は「戒名とは?意味や由来、授かる際の注意点を解説」について簡単に説明します。
戒名(読み方:かいみょう)とは、仏教の教えを学び、仏教修行の上で戒律を守ることを約束した証しとして、また、仏弟子となった証しとして与えられる名前で、仏様の世界における故人の新しい名前のことです。
本記事では、戒名の意味や歴史、授かる際のポイントについて解説します。
1.戒名とは?意味と役割

戒名は、原則として菩提寺(読み方:ぼだいじ)のご住職から授かります。
戒名は、人が亡くなった後につけられるものだと考えている方が多いと思いますが、厳しい戒律を守り、修行をして、経典を勉強した人が仏門に入り、仏弟子となった証しとして授かる名前なので、元々は出家した僧侶や信者が生前に与えられるものです。
現在では、戒名を授かることで迷いなく極楽浄土へ導かれるとの考えから、死後に戒名を授けていただくことが一般的になりました。
戒名は、お墓や位牌に刻まれます。
戒名の構成
戒名は主に以下の4つの要素で構成されます。
- 院号、院殿号(社会的貢献度が高い人に与えられる最高位の称号)
- 道号(故人の人柄や性格を表す)
- 戒名(仏の世界における呼び名)
- 位号(性別、年齢、社会的地位などによって決まる尊称)
2.戒名の由来と歴史
戒名の起源は、古代インドの仏教にまで遡ります。
日本では鎌倉時代以降、広く一般にも普及しました。
なぜ戒名を授かるのか?
- 家族の安心:戒名を授かることで、家族が安心して供養を続けられる
- 仏弟子としての証明:仏の教えに従う者としての名前
- 供養のため:戒名があることで、故人を正式に仏弟子として供養できる
3.戒名を授かる際の注意点
戒名を授かる際には、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
戒名の種類と費用
戒名には様々なランクがあり、それによって授与される費用も異なります。
- 信士・信女(一般的な位号)
- 居士・大姉(一定の功績がある人向けの位号)
- 院号付き(格式が高く、費用も高額になる)
お寺との相談
戒名は菩提寺(先祖代々の墓がある寺)と相談しながら決めるのが一般的です。
あらかじめどのような戒名を授かりたいのか希望を伝えておくとよいでしょう。
お墓への刻字
戒名は墓石に刻まれるため、戒名を授かった後は石材店に相談しましょう。
生前に戒名を授かり、墓石に彫刻した場合は、文字の上に赤色を塗り入れることで、まだ、生きているという証しを示すことができます。
4.まとめ
戒名は仏教以外の宗教では使用しません。
また、仏教の宗派によっても「法名(ほうみょう)」や「法号(ほうごう)」など表現のしかたが変わり、その意味合いも異なります。
地域によっては「戒名」のことを「法名」、「法名」のことを「戒名」と呼んでいるところもあります。
戒名は仏門に入る証であり、故人を供養する上で大切な役割を果たします。
授かる際は、戒名の意味やランク、費用を理解し、お寺とよく相談することが大切です。