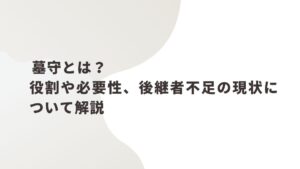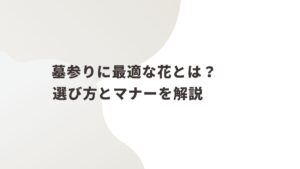「墓じまい」しないとどうなる?放置のリスクと適切な対処法
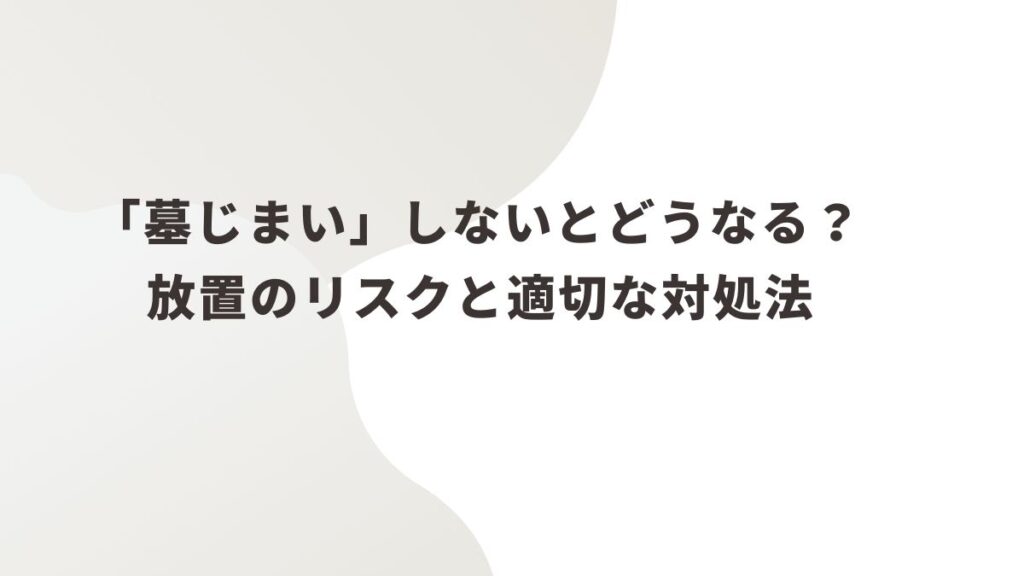
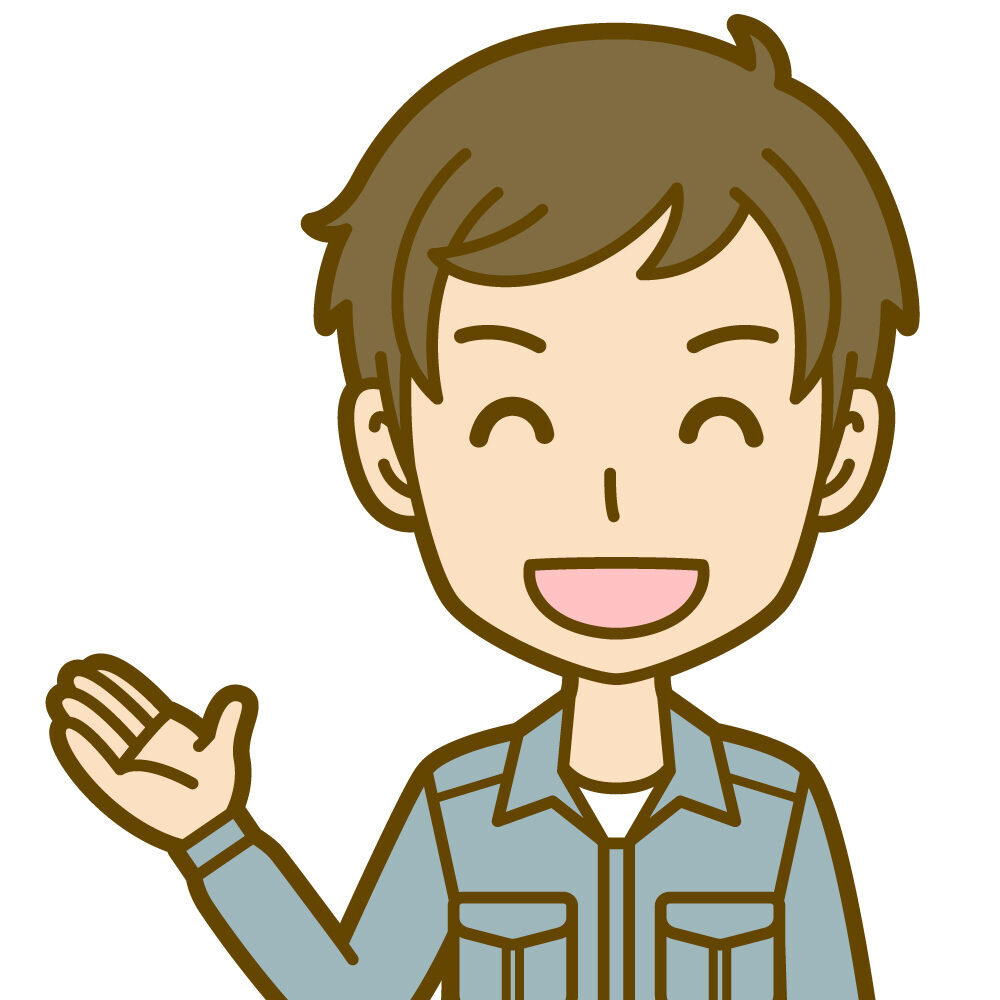
業界経験この道30年の石職人です。今回は「墓じまい」しないとどうなる?放置のリスクと適切な対処法について簡単に説明します。
近年、「墓じまい」を検討する人が増えています。しかし、何らかの理由で墓じまいをしないまま放置すると、さまざまな問題が発生する可能性があります。本記事では、墓じまいをしない場合に起こるリスクや、その対処法について詳しく解説します。
目次
1.墓じまいをしないとどうなる?主なリスク

墓じまいをせずに放置すると、以下のような問題が生じる可能性があります。
- 無縁墓になってしまう:
継承者がいない、または管理できなくなると、お墓が無縁墓(読み方:むえんぼ、又は、むえんばか)として扱われる可能性があります。 - 管理費の滞納で撤去されることも:
霊園や寺院の管理費が支払われなくなると、一定期間後に墓石が撤去されることがあります。 - 墓石の倒壊リスク:
管理されていない墓地では、経年劣化による墓石の倒壊が起きて、他のお墓に迷惑が掛かることがあります。 - 遺族に負担がかかる:
将来的に子どもや親族が墓を管理できなくなった場合、墓じまいの手続きや費用が大きな負担となることがあります。
2.無縁墓になるとどうなる?管理の実態
無縁墓とは、管理する人がいなくなった墓のことです。
多くの自治体や寺院では、一定期間管理が滞ると無縁墓と認定し、合葬墓などに改葬されることがあります。
無縁墓の対応は管理者ごとに異なりますが、一般的には以下の流れになります。
- 無縁墓として公告(新聞や墓地内掲示板に告知)
- 一定期間(通常1~3年)管理者からの申し出を待つ
- 申し出がなければ墓石の撤去・合葬墓へ改葬
このように、墓じまいをしないまま放置すると、意図せずして改葬されてしまうケースもあります。
3.墓じまいをしない理由とその影響
墓じまいを進めない理由として、以下のようなものが挙げられます。
- 費用がかかるため、先延ばしにしている
- 親族間で意見が合わない
- 手続きが面倒で、どこから始めればいいか分からない
- 先祖代々のお墓を手放すことに抵抗がある
しかし、墓じまいをせずに放置してしまうと、最終的に自治体や霊園の判断で処理されることもあり、ご遺族にとっても良い形ではありません。
4.墓じまいを検討するタイミングと適切な進め方
墓じまいを検討するタイミングとして、以下のようなケースがあります。
- 高齢になり、お墓参りが難しくなったとき
- 後継者がいなくなったとき
- 管理費が支払えなくなったとき
- 遠方の墓を近くに移したいと考えたとき
墓じまいを進める際の流れは以下の通りです。
- 親族と相談し、合意を得る
- 墓地の管理者(寺院や霊園)に相談する
- 遺骨の移転先(永代供養墓・合葬墓・納骨堂など)を決める
- 僧侶によるお墓の閉眼供養を行う
- 石材店に依頼して墓石の撤去を行う
- 遺骨を移転して、墓じまいを完了させる
5.墓じまいの費用と手続きのポイント
墓じまいには費用がかかるため、事前に相場を把握しておくことが大切です。
| 項目 | 費用相場(円) |
|---|---|
| 墓石の撤去費用 | 20万~50万円 |
| 永代供養墓への改葬費用 | 5万~50万円 |
| 閉眼供養(僧侶へのお布施) | 2万~5万円 |
| 改葬許可申請費用 | 0円~数千円 |
費用を抑えるポイントとしては、複数の石材店に見積もりを依頼することや、安価な永代供養墓や合葬墓を選ぶことが挙げられます。
6.墓じまいの代替案とは?供養の選択肢
墓じまいをせずに供養を続けたい場合、以下のような選択肢もあります。
- 永代供養墓を利用する:個別の墓を持たずに供養してもらう
- 納骨堂を利用する:室内に遺骨を安置するタイプの供養施設
- 散骨を検討する:自然葬として海や山に散骨する
これらの方法を検討することで、無縁墓になるリスクを回避しつつ、適切な供養を続けることができます。
7.まとめ
墓じまいをしないまま放置すると、無縁墓として扱われたり、遺族に負担がかかったりする可能性があります。将来のことを考え、早めにご家族や親族と話し合い、適切な方法で墓じまいを進めることが大切です。