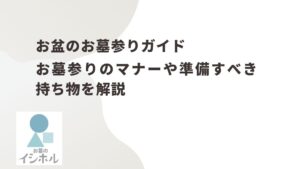お盆とお彼岸の違いとは?それぞれの意味と供養の仕方
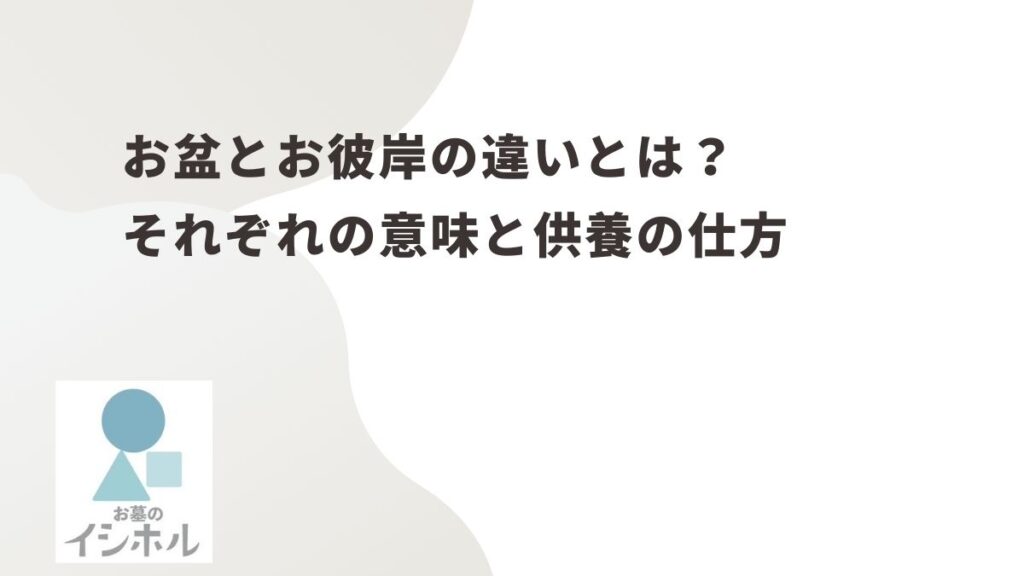
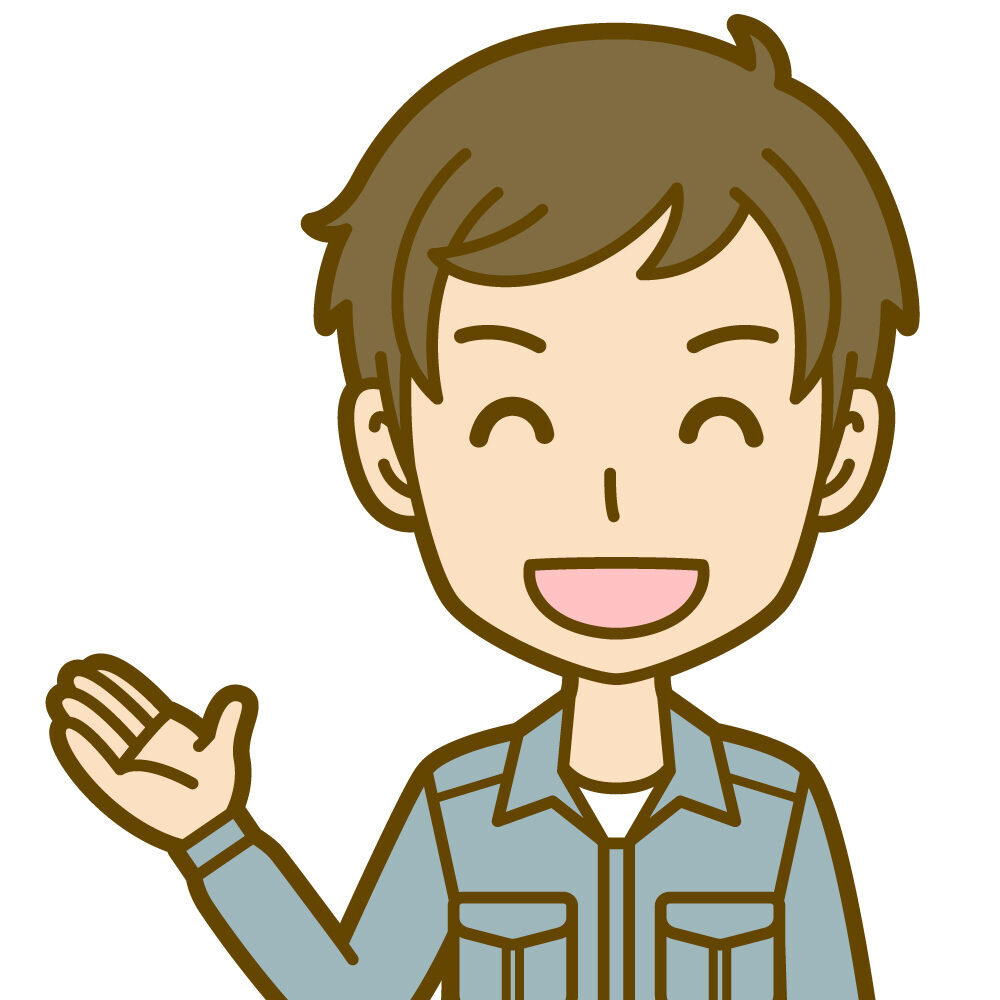
業界経験この道30年の石職人です。今回は「お盆とお彼岸の違いとは?それぞれの意味と供養の仕方」について簡単に説明します。
この記事では、お盆(読み方:おぼん)とお彼岸(読み方:おひがん)の違いを解説し、それぞれの由来や供養の方法について解説します。
ご先祖様への供養をより丁寧に行いたい方は、ぜひ参考にしてください。
1.お盆とは?その意味と由来

お盆(盂蘭盆会)は、ご先祖様の霊をお迎えし、供養する日本の伝統的な行事です。
一般的には8月13日から16日(地域によっては7月)に行われます。
【お盆の由来】
お盆の由来は、仏教の「盂蘭盆経(読み方:うらぼんきょう)」にあります。
お釈迦様の弟子である目連尊者が亡き母を救うために、供養を行ったと説いたことが最初とされています。
2.お彼岸とは?その意味と由来
お彼岸は、春分の日(3月)と秋分の日(9月)を中心とした7日間に行われる仏教行事です。
この期間は、昼と夜の長さがほぼ同じになり、仏教では極楽浄土に最も近い期間とされています。
【お彼岸の由来】
「彼岸」とは、仏教における悟りの世界(極楽浄土)と、煩悩と迷いの多い現世(此岸)が最も近づく時期で、思いが通じやすくなる期間と言われています。
3.お盆とお彼岸の違い
| 項目 | お盆 | お彼岸 |
|---|---|---|
| 時期 | 8月(または7月) | 春分・秋分の日を中日とした7日間 |
| 目的 | ご先祖様の霊を迎えて供養 | 極楽浄土に思いをはせ、善行積む |
| 供養方法 | お墓参り、仏壇へのお供え、迎え火・送り火、盆踊り | お墓参り、仏壇へのお供え、善行を行う |
| 宗教的背景 | 仏教+民間信仰 | 仏教 |
お盆は「ご先祖様を迎えて供養する行事」、お彼岸は「自分自身が善行を積む行事」としての側面もあることが特徴です。
4.それぞれの供養の仕方
【お盆の供養】
- 迎え火:
ご先祖様のお迎えのために玄関先で火を灯します。 - お墓参り:
ご先祖様のご供養のため、お墓の掃除やローソクを灯しお線香を供えます。 - 精霊馬(読み方:しょうりょううま):
ナスやキュウリで作った馬や牛の乗り物を用意し、霊の移動を助けます。 - 盆踊り:
ご先祖様の霊を慰めるために行われる伝統行事です。
【お彼岸の供養】
- お墓参り:
春と秋の2回行うことで、よりご先祖様との縁を守ります。 - 仏壇のお供え:
「ぼたもち(春)」や「おはぎ(秋)」をお供え、感謝の気持ちを表します。 - 六波羅蜜の実践:
仏教の教えに基づき、「布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧」を行うことが推奨されます。
5.まとめ

お盆とお彼岸は、どちらも大切な先祖供養の機会ですが、その意味合いと方法には違いがあります。
お盆は先祖の霊を迎え入れる行事であり、お彼岸は極楽浄土にいる先祖を思い、敬う期間です。
どちらの行事も、現代のライフスタイルに合わせて柔軟に対応することが可能です。
例えば、お墓がない場合でも、自宅で花を飾ったり、お供えをしたりすることで、先祖を敬う気持ちを表すことができます。
大切なのは、これらの行事を通じて先祖に感謝し、家族の絆を深めることです。
伝統的な方法にこだわらず、自分なりの方法で先祖を敬う気持ちを表現することが、現代の供養の在り方として重要です。
※ 地域によって様々な風習があります。また、宗派により教えが異なる場合がありますので、菩提寺の宗旨に習うことが大切です。