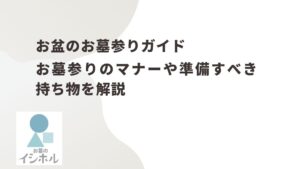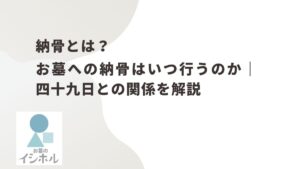法要とは?四十九日・一周忌・三回忌の違いを解説
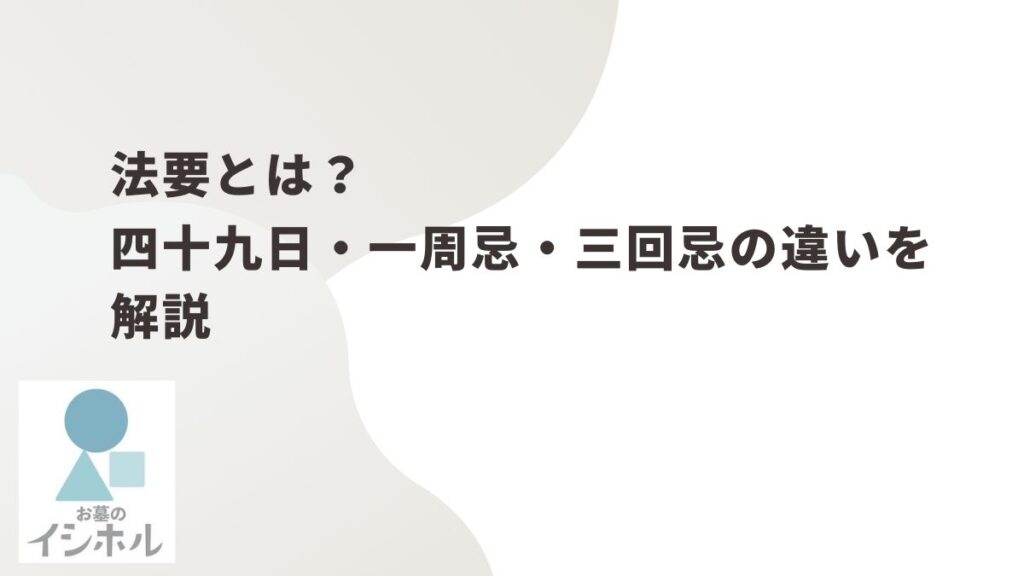
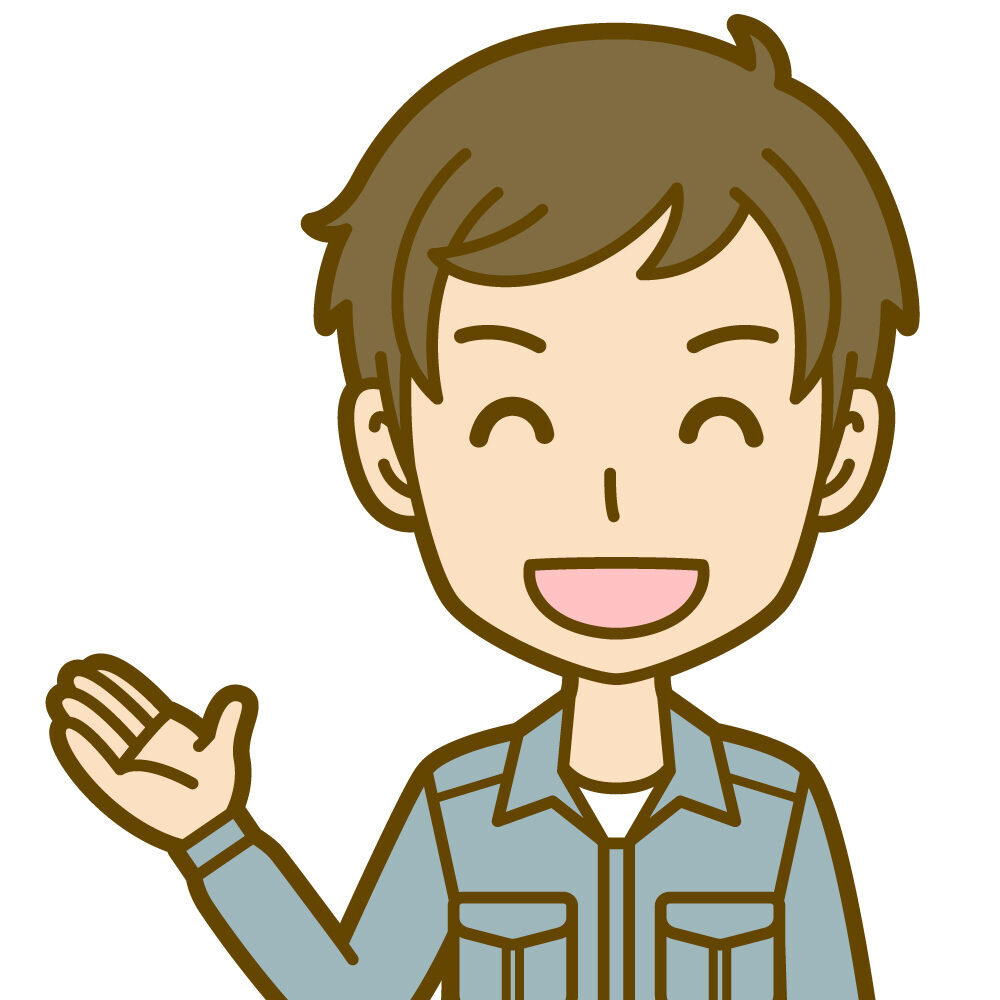
業界経験この道30年の石職人です。今回は「法要とは?四十九日・一周忌・三回忌の違いを解説」について簡単に説明します。
法要とは、故人を偲び供養(読み方:くよう)するための仏教の儀式です。
特に「四十九日」「一周忌」「三回忌」は、ご遺族にとって重要な節目の法要となります。
それぞれの意味や違いを理解することで、正しい準備を進めることができます。
1.法要とは?その意味と目的

法要とは、故人(読み方:こじん)の冥福を祈り、仏の教えに従ってご遺族が故人を偲ぶ大切な機会です。
僧侶をお招きし、お経をあげていただき、遺族や親族が集まって故人を偲びます。
しかし、四十九日、一周忌、三回忌など、様々な法要の違いを正確に理解している人は少ないかもしれません。
この記事では、法要の意味や種類、特に四十九日、一周忌、三回忌の違いについて解説します。
2.四十九日法要とは?意味と流れ
四十九日法要(読み方:しじゅうくにちほうよう)は、故人が亡くなってから49日目に行われる重要な法要です。
元来、仏教では、亡くなった人の魂は49日間をかけて冥界を旅し、極楽浄土に行くための裁判が7日毎に行われ、7回目の49日で審判が下されるとの考えがあるからです。
そのため、四十九日目は故人の成仏を願い、供養を行う大切な日とされています。
【四十九日法要の意味】
- 故人の魂が極楽浄土に旅立つまでの期間とされる
- ご遺族の深い悲しみが和らぐ時期とも考えられている
- 喪に服する期間の区切りとなる
- 故人の魂の旅立ちとご遺族の喪明けの区切り
【四十九日法要の流れ】
- 僧侶を呼んで読経を行う
- 遺族・参加者が焼香を行う
- 僧侶による説法
- 参加者とともに会食をする(精進落とし)
この法要の際に納骨(読み方:のうこつ)を行う方や、この法要までには位牌の準備や、お墓への故人の名入れ(追加彫り)を行うケースが多いです。
3.一周忌法要とは?何をするのか
一周忌法要(読み方:いっしゅうきほうよう)は、故人が亡くなってから満1年後に行われる法要です。
「一周」とは、暦が1周したことを意味します。
四十九日法要と並んで、遺族にとって重要な法要の一つです。
【一周忌法要の意味】
- 故人の命日に近い日を選び、家族や親族、仲間と共に供養を行う
- 四十九日法要に次いで重要な法要とされる
- 故人の冥福を共に祈り、ご遺族の心の区切りとする
- 故人との別れを受け入れ、新たな一年の始まり
【準備と流れ】
- 僧侶を手配し、法要を行う
- お墓参りをする
- 会食を行う、故人の思い出を語る
一周忌の準備は、通常2ヶ月前から始めることが望ましいとされています。
一周忌法要は、ご遺族や親族、または、多くの友人が集まる最後の大規模な法要となることが多いです。
4.三回忌法要とは?意味と特徴
三回忌法要(読み方:さんかいきほうよう)は、故人が亡くなってから2年後(満2年目)に行われる法要です。
「三回」とは、3回目の命日を意味します。
【三回忌法要の意味】
- 故人を偲び、さらなる供養をおこなう
【三回忌法要の特徴】
- 家族や親族のみの少人数で行うことが多い
- 一周忌よりも簡略化されることが多い
三回忌法要の後も七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、五十回忌と続いていきます。
三十三回忌や五十回忌で弔い上げとするところが多いです。
5.法要を行う際の注意点

① 法要の日程を早めに決めること
特に、四十九日や一周忌は家族や親族が集まるため、早めに日程を決めることが大切です。
②僧侶の手配と会場の準備
菩提寺がある場合は、早めに連絡を取り、会場(自宅・寺院・斎場など)を決めましょう。
③案内状の送付
法要の1ヶ月前までには案内状を送りましょう
④ 供物や返礼品の準備
参加者には香典やお供え物を持参するのが一般的なので、返礼品をご用意しておきます。
⑤お布施の準備
寺院への感謝の気持ちとしてのお布施を用意する。
6.まとめ
法要は、故人を偲び、供養する大切な機会です。
四十九日、一周忌、三回忌はそれぞれ異なる意味を持ち、故人との関係を再確認し、生きることの意味を考える機会となります。
法要を通じて、故人への感謝の気持ちを表すとともに、家族や親族の絆を深めることができるでしょう。