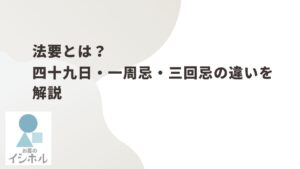納骨とは?お墓への納骨はいつ行うのか|四十九日との関係を解説
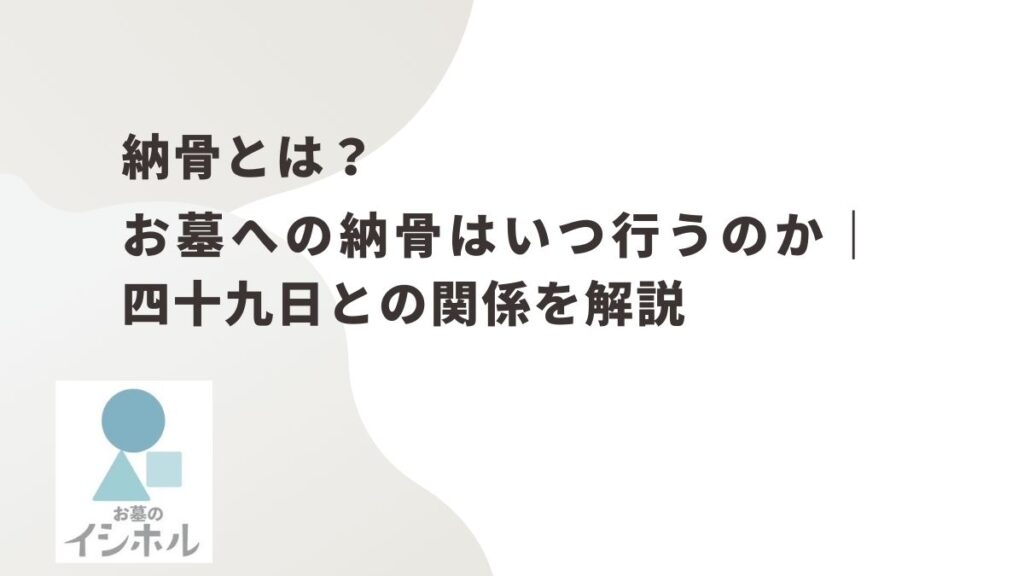
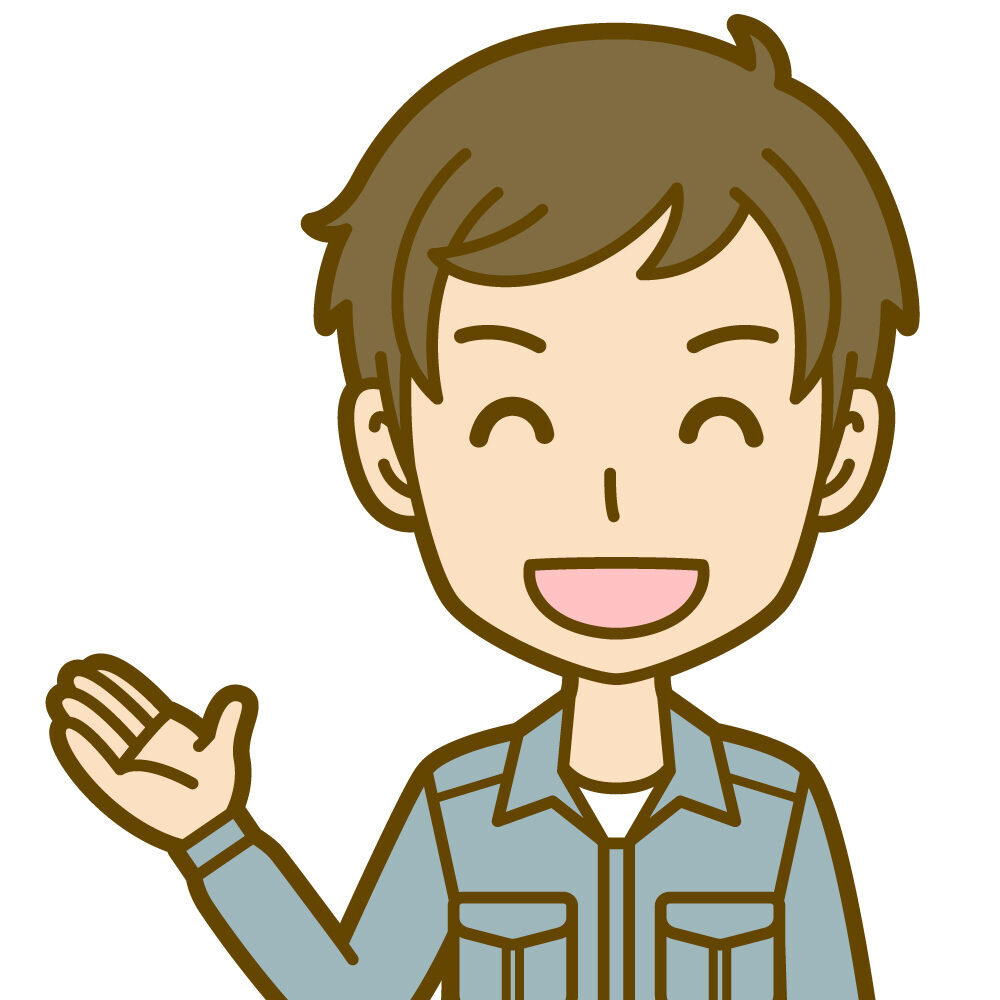
業界経験この道30年の石職人です。今回は「納骨とは?お墓への納骨はいつ行うのか|四十九日との関係を解説」について簡単に説明します。
納骨(読み方:のうこつ)とは、大切な人を見送った後、ご遺骨をお墓に納めることです。
納骨は、四十九日法要(読み方:しじゅうくにちほうよう)などの法要(読み方:ほうよう)と合わせて行われることが一般的ですが、この日に必ず行われなければいけないわけではありません。
いつ納骨を行うべきか、この記事では、納骨の適切な時期や四十九日との関連性、そして納骨の準備から当日の流れまでを解説します。
1.納骨とは?その意味と役割
日本では火葬が一般的であり、火葬後に骨壺へ収めたご遺骨を、一時的に自宅や寺院に安置し、適切な時期にお墓へ納骨します。

2.納骨いつ行う?四十九日との関係
納骨の時期として最も多いのが「四十九日法要」の日です。
仏教では、故人が亡くなった日から四十九日は「中陰」とされ、この期間を過ぎると故人はあの世へ旅立つと考えられています。
事情によっては、四十九日を過ぎてから納骨を行う場合もあります。
同様に、墓石の準備が間に合わない場合や、遠方に住む親族の都合で延期することもあります。
近年では、仕事や生活、金銭的な事情から、葬儀自体を簡略化し、「初七日(読み方:しょなのか)〈7日目〉」、「二七日(読み方:ふたなのか)〈14日目〉」、「三七日(読み方:みなのか)〈21日目〉」に納骨を済ませる方も増えております。
コロナを経て、仏事の簡略化が進んでいるといえます。
3.宗派や地域による納骨時期の違い
宗派や地域によって、納骨のタイミングには違いがあります。
- 曹洞宗・臨済宗:四十九日に納骨するのが一般的
- 浄土真宗:四十九日を待たず、火葬後すぐに納骨する場合もある
- 神道(神式):五十日祭の後に埋葬する
- 沖縄や奄美地方:旧暦の特定の時期に納骨する風習がある
このように、宗派や地域の習慣を確認した納骨の時期を決めることが大切です。
4.納骨の流れと準備すべきこと

納骨をスムーズに行うためには、事前に準備が必要です。
① 納骨前の準備
- お墓の手配:墓石の準備や、納骨室の確認
- 納骨許可証の取得:火葬場で発行された「埋葬許可証」を墓地管理者へ提出
- 僧侶や神職への依頼:お経や祝詞をあげて頂く場合、事前に予約が必要です
- 用意するもの:墓地の使用許可証・お位牌・数珠・花・お供え物・線香・ろうそく・お布施・墓石への故人の名入れ追加彫りを済ませておくなど
② 納骨当日の流れ
- お墓の清掃と供物を供える
- 遺骨をお墓に納める
※お墓の納骨口の石が動かせないことがあるので、必要な場合は、石材店に予約をします。 - 墓前での読経・法要(または神事)
- 参加者による焼香
- 会食
※ 地域や菩提寺の方針によって納骨の流れは異なります。
納骨の際は、家族や親族で手を合わせ、故人を偲ぶ時間を大切にしましょう。
5.納骨の方法
納骨の方法は主に3つあります
- 骨壺のまま納める
- 綿素材の納骨袋に入れて納める
- お墓の中に直にお骨をまく(散骨)
骨壺で収めると、永年お骨は壺の中にそのままの状態で残ります。
近年では、輪廻転生の思考から、お骨を土に還すということで、骨壺から空けて納骨される方が多いです。
地域や宗教、宗派によって納骨の適切な方法が異なるため、事前に菩提寺(読み方:ぼだいじ)や石材店に確認することが重要です。
6.まとめ
納骨の時期は四十九日が一般的ですが、事情に応じて柔軟に対応することも可能です。
宗派や地域による違いを考え、事前に準備を整えることで、スムーズな納骨ができます。
故人の供養を大切にしながら、菩提寺にも相談しながら納骨のタイミングを決めましょう。