埋葬とは?意味や種類、日本の伝統的な埋葬方法を解説
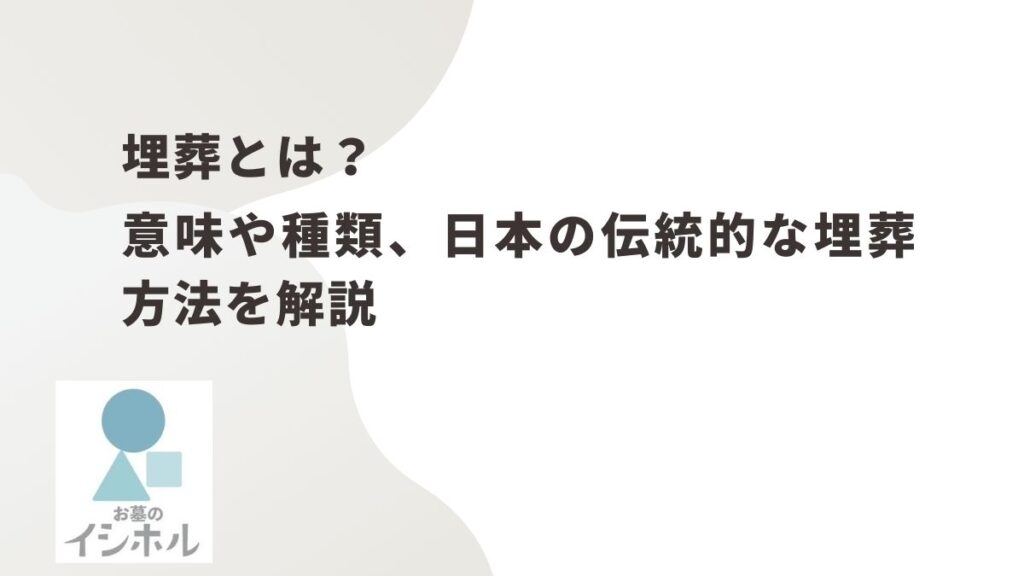
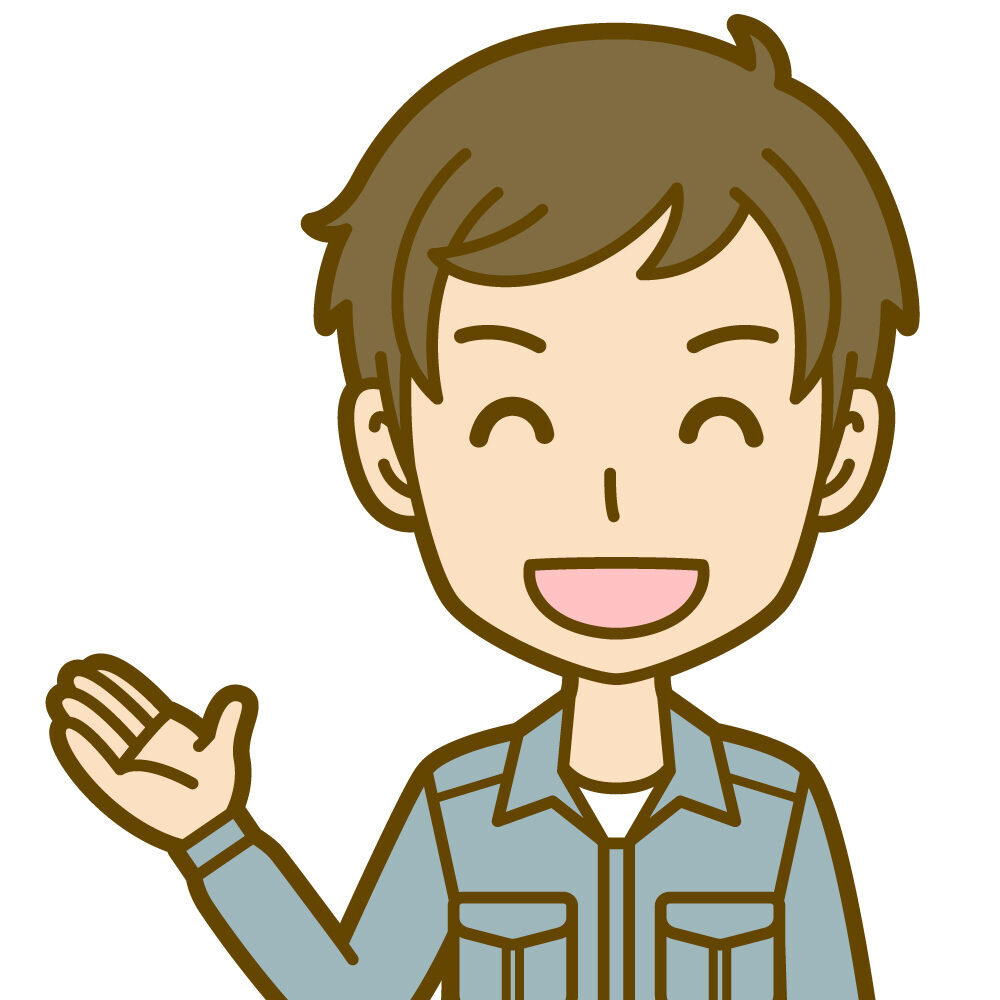
業界経験この道30年の石職人です。今回は「埋葬とは?意味や種類、日本の伝統的な埋葬方法を解説」について簡単に説明します。
埋葬(読み方:まいそう)とは、亡くなった方の遺体や遺骨を土や墓に納めることです。
古来より、さまざまな宗教や文化に応じた埋葬方法が存在し、日本でも時代とともにその形が変化してきました。
本記事では、埋葬の基本的な意味から、日本における伝統的な埋葬方法や近年の動向まで解説します。
1.埋葬とは?その意味と歴史

埋葬とは、亡くなった方のご遺体やご遺骨を地中に納める葬送の一種です。
語源としては「土に埋めて葬る」ことを意味し、古代から世界各地で行われてきました。
日本においても、縄文時代には土葬が主流であり、弥生時代になると墳墓文化が発展しました。
墓地の埋葬等に関する法律では、埋葬は「死体を土中に葬ること」と定義されています。
しかし、慣用的には火葬後の遺骨を墓地や納骨堂に収納することも埋葬と呼ぶことがあります。
2.日本における伝統的な埋葬方法
日本の埋葬(読み方:まいそう)方法は、時代とともに変化してきました。
代表的な方法を紹介します。
・ 土葬
かつては日本でも土葬が一般的でした。
遺体を直接土に埋める方法で、江戸時代までは多くの地域で行われていました。
しかし、衛生面や都市部の土地不足の問題から、現在ではほとんど行われていません。
・ 火葬
現在、日本で最も一般的なのが火葬です。
遺体を火葬場で焼却し、遺骨を骨壺に納めて埋葬します。
法律により、原則として火葬が義務付けられており、ほとんどの人が火葬をおこなっております。
・墓地埋葬
火葬後の遺骨は、墓地や納骨堂に納められます。
多くの家庭では先祖代々の墓に納骨する形が一般的です。
3.近年の埋葬の変化
近年、ライフスタイルの変化に伴い、新しい埋葬の形が増えています。
・ 樹木葬
墓石を設置せず、樹木の下に遺骨を埋葬する方法です。
自然と共生する形で供養できるため、環境保護の観点から人気を集めています。
・散骨
海や山などに遺骨を撒く方法です。
法律的には「節度を持って行うこと」が求められますが、近年では海洋散骨や宇宙葬など多様な選択肢が登場しています。
・永代供養墓(合葬墓)
継承者がいない場合や、お墓の維持が難しい場合に選ばれる埋葬方法です。
寺院や霊園が管理し、永代供養墓(合葬墓)に納める形が一般的です。
4.埋葬にかかる費用と手続き

〈埋葬にかかる費用〉
埋葬費用は方法によって異なります。
- 火葬費用:数千円~10万円程度
- 墓地購入費用:100万~300万円程度
- 合葬墓:5万~50万程度
- 納骨堂:10万~100万円程度
- 樹木葬:20万~100万円程度
- 散骨:5万~30万円程度
〈埋葬に必要な手続き〉
- 死亡届の提出(市区町村役場)
- 火葬許可証の取得
- 火葬の実施
- 納骨許可証の取得と埋葬
〈埋葬の流れ〉
- 遺骨埋葬許可証の取得
- 埋葬場所の選定(墓地や納骨堂など)
- 法要の手配(希望する場合)
- 石材店への作業依頼(お墓に故人の名前を彫る、または納骨口を開けるなど)
- 必要な持ち物の準備(供花や線香などのお供え物など)
- 埋葬の実施
5.まとめ
埋葬は、故人を偲び、供養する大切な儀式です。
また、故人との最後のお別れであると同時に、新たな形での関係の始まりでもあります。
現代では多様な選択肢があり、それぞれの価値観や状況に応じた方法を選ぶことができます。
埋葬に関する疑問や不安がある場合は、葬儀社や石材店、菩提寺に相談することをおすすめします。


