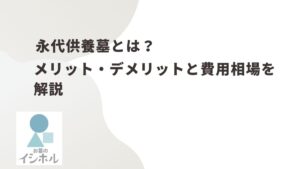お盆とは?意味や由来、迎え方を解説
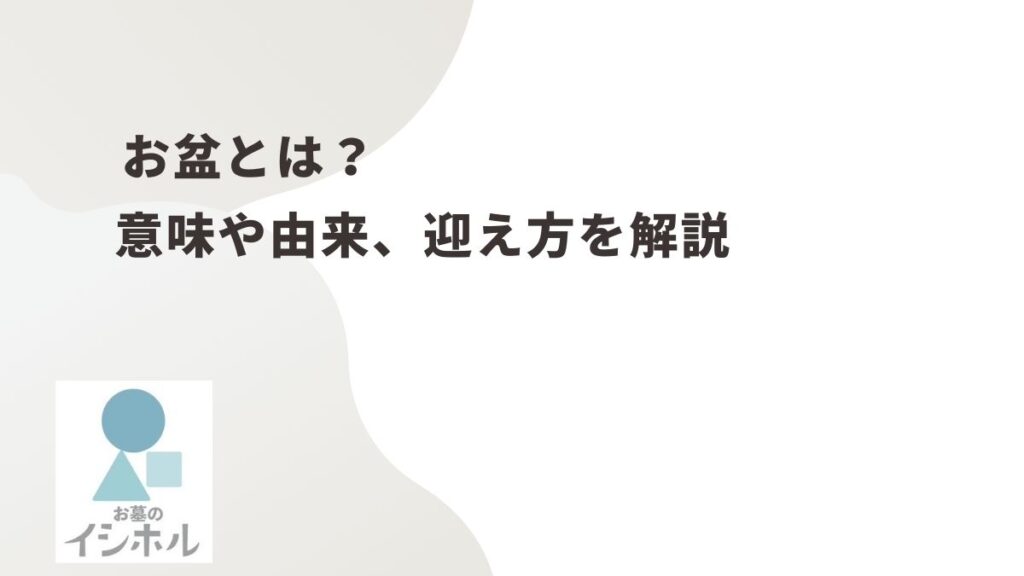
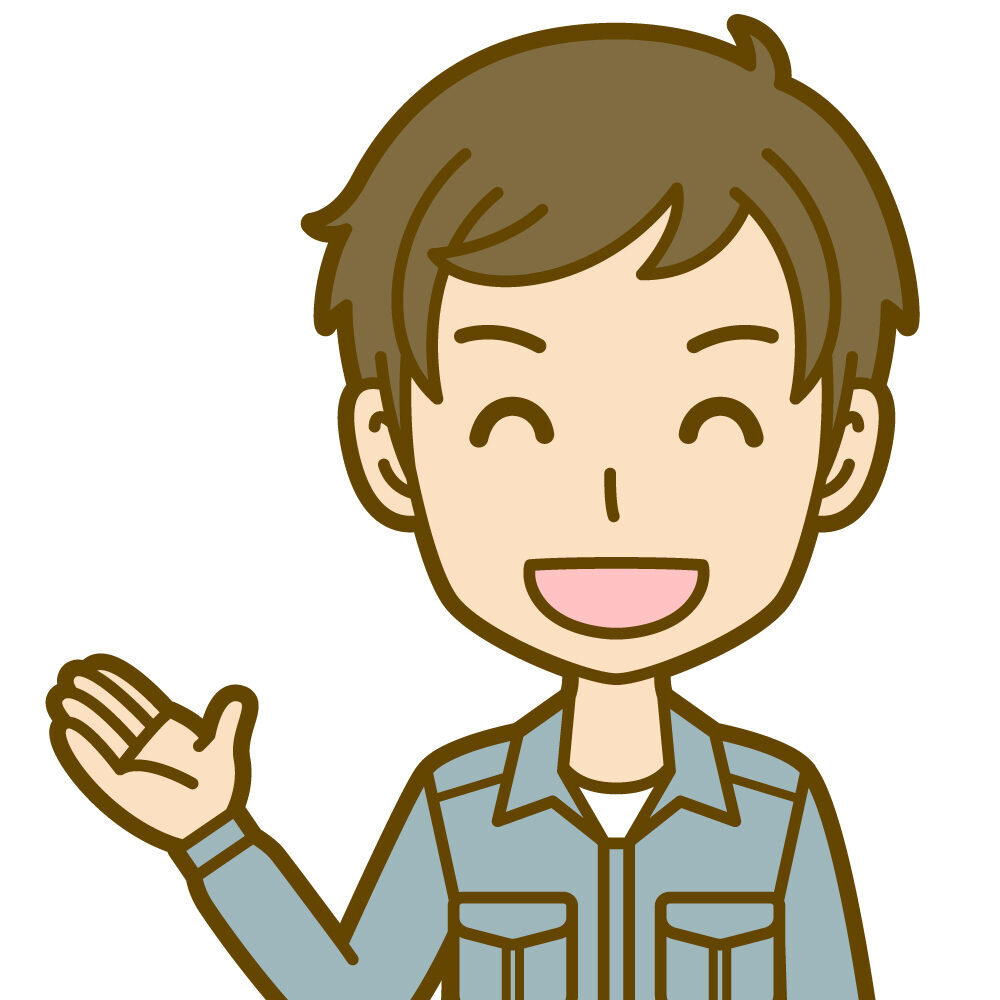
業界経験この道30年の石職人です。今回は「お盆とは?意味や由来、迎え方を解説」について簡単に説明します。
お盆は、日本の伝統的な行事の一つであり、ご先祖様を供養する大切な期間です。
しかし、お盆の意味や正しい迎え方を詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、お盆の由来や風習、現代のお盆の過ごし方について解説します。
1.お盆とは?その意味と由来

お盆(盂蘭盆会)は、仏教に由来する行事で、ご先祖様の霊を迎え入れ、供養する期間です。
もともとは「盂蘭盆経」に由来し、餓鬼道に落ちた母親を救うためにお供え物をしたことが始まりとされています。
日本では、仏教とともに伝わり、平安時代には貴族社会で、江戸時代には庶民の間でも広く行われるようになりました。
現在でも全国各地でお盆の行事が行われ、地域によって異なる風習が残っています。
2.お盆の基本的な過ごし方
お盆には、以下のような風習があります。
➀ 迎え火と送り火
お盆の始まりには、ご先祖様の霊が迷わず帰ってこられるように「迎え火」を焚きます。
お盆の終わりには「送り火」を焚き、ご先祖様を再び送り出します。
② 棚経
棚経(読み方:たなぎょう)は、僧侶を自宅に招いて、仏壇や精霊棚の前でお経を読んでもらう習慣です。
③ お墓参り
お盆の期間中は、お墓参りをしてご先祖様に感謝の気持ちを伝えます。
お花や線香を供え、お墓をきれいに掃除することも大切です。
④ お供え物
仏壇や精霊棚に、ご先祖様の好きだった食べ物やお供え物を用意します。
地域によっては「ほおずき」を飾る風習もあります。
3.現代のお盆の過ごし方と注意点
近年では、ライフスタイルの変化により、お盆の過ごし方も多様化しています。
➀ 帰省せずにオンラインで供養
遠方に住んでいる方は、お墓参りが難しいこともあります。
その場合、オンライン供養を利用する方法もあります。
② お盆の時期と地域差
お盆の時期は、地域によって異なります。
多くの地域では8月13日~16日に行われますが、7月に行う地域もあります。
③ お盆期間中のマナー
お盆の時期は、仏教の行事を意識しながら、慎み深く過ごすことが大切です。
また、親族が集まる機会でもあるため、家族と共に故人を偲ぶ時間を持ちましょう。
4.まとめ
お盆は、ご先祖様を供養し、家族の絆を深める大切な行事です。
遠方に住む家族が実家に帰省する機会でもあります。
家族揃って先祖の墓参りをしたり、一緒に食事を楽しんだりする時間を大切にする人が多いです。
伝統的な迎え方や風習を大切にしながら、自分たちのライフスタイルに合った形で心豊かにお盆を過ごしましょう。